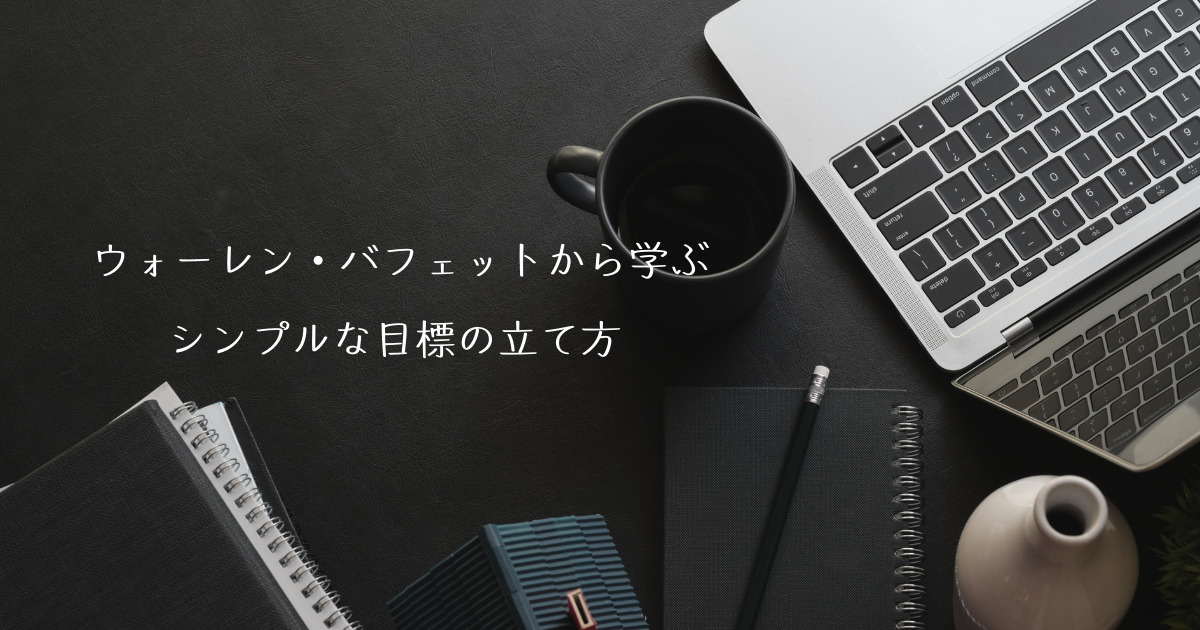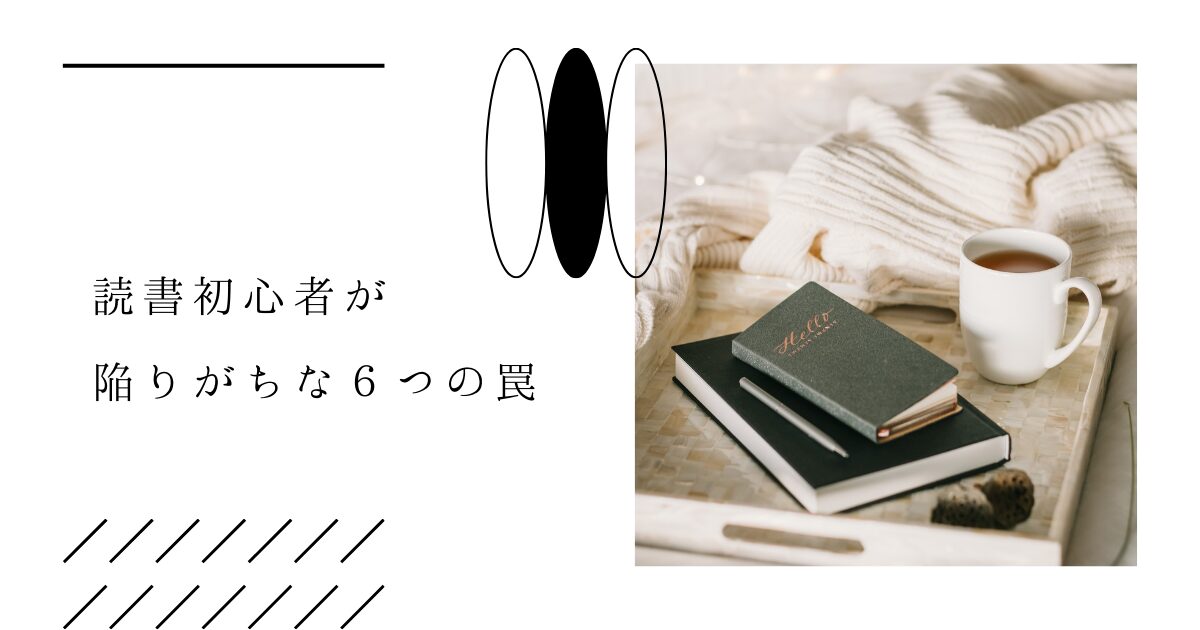読書は、知識を増やし、自己肯定感を高め、新たな気づきを与え、リラックス効果をもたらすなど、多くのメリットをもたらします。
しかし、読書には落とし穴やデメリットも存在します。
この罠にハマってしまうと、せっかく読書を始めようと意気込んだのに途中で放棄してしまう、スキルアップやモチベーションを高めるためので読書のはずが、逆にモチベーションが下がってしまった、という事態に陥ります。
そこで今回は、読書の罠について解説し、読書を最大限に活かすためのポイントを紹介していきたいと思います。
読書を途中で諦めちゃった人や、読書をしても思うような効果が得られないという人はぜひご覧になっていってください。
読書で陥りがちな6つの罠


読書の罠にを回避するためには、以下の点に注意する必要があります。
- 目的が明確になっていない
- 特定の著者を妄信してしまう
- 一気に読もうとしてしまう
- 自分の考えを押し付ける
- 悪い姿勢や視力の低下
- インプットばかりになっている
目的が明確になっていない
「読書は良いこと」ということはわかるものの、実際に何をどう読んでだらいいのか迷ってしまうことがあります。
これは、読書の目的が明確になっていないことが原因です。
「なんとなく読書をしてみよう」ではなく、「なぜ読書をするのか」目的を明確にすることが大切です。
例えば、
| 目的 | 本の種類 |
| スキルアップ | ビジネス書、資格取得関連の本 |
| 体重を減らしたい | ダイエット関連の実用書 |
| ポジティブになりたい | 自己啓発書 |
| リラックス | 小説、エッセイ、マンガ |
| 創造性 | ファンタジー小説、SF小説 |
など、目的によって選ぶべき本のジャンルも変わってきます。
読書の効果を実感することは、読書の習慣化にも繋がります。
まずは読書の目的を明確にしておいきましょう。
特定の著者を妄信してしまう
本には著者の思いが込められており、信憑性も高いものです。
読者の中には、特定の著者のファンになる方も多いかと思います。
しかし、「この著者の言っていることはすべて正しい」と、著者や、本に書かれている内容を鵜呑みにするのは危険です。
確かに本は信憑性が高いですが、盲信してしまえば視野は狭くなり、冷静な判断ができなくなってしまう可能性があります。
一気に読もうとしてしまう


読書を楽しいと感じると、たくさんの本を一気に読みたくなるものです。
しかし、一気に読んでしまうと、本の内容がまったく頭に入ってこなくなる可能性があります。
人にもよりますが、人間の集中力は長く続かず、集中力の持続時間は50分程度といわれています。
長時間読書をする場合は、途中で休憩を挟んだり、何日かに分けて読むようにしましょう。
スキマ時間に読書をするのもおすすめです。
スキマ時間は短時間なので集中力を維持したまま本を読むことができます。
一つ一つのスキマ時間は短時間ですが、積み重ねると結構まとまった時間になります。
スキマ時間を上手に活用したい場合は、こちらの記事を参考にしてみてください。
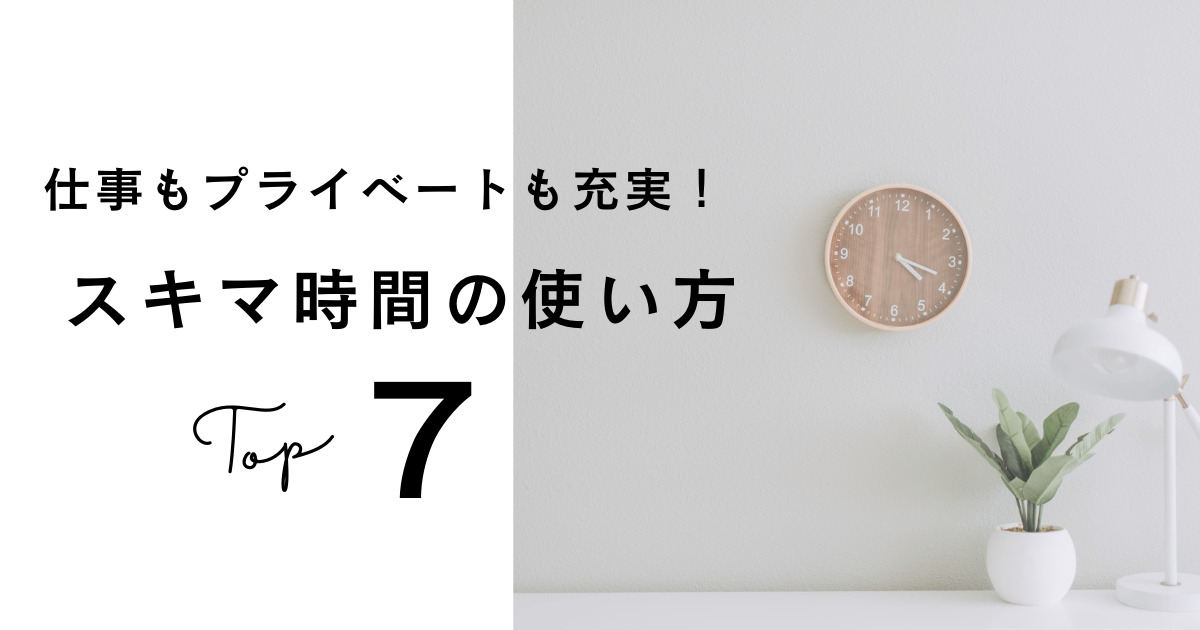
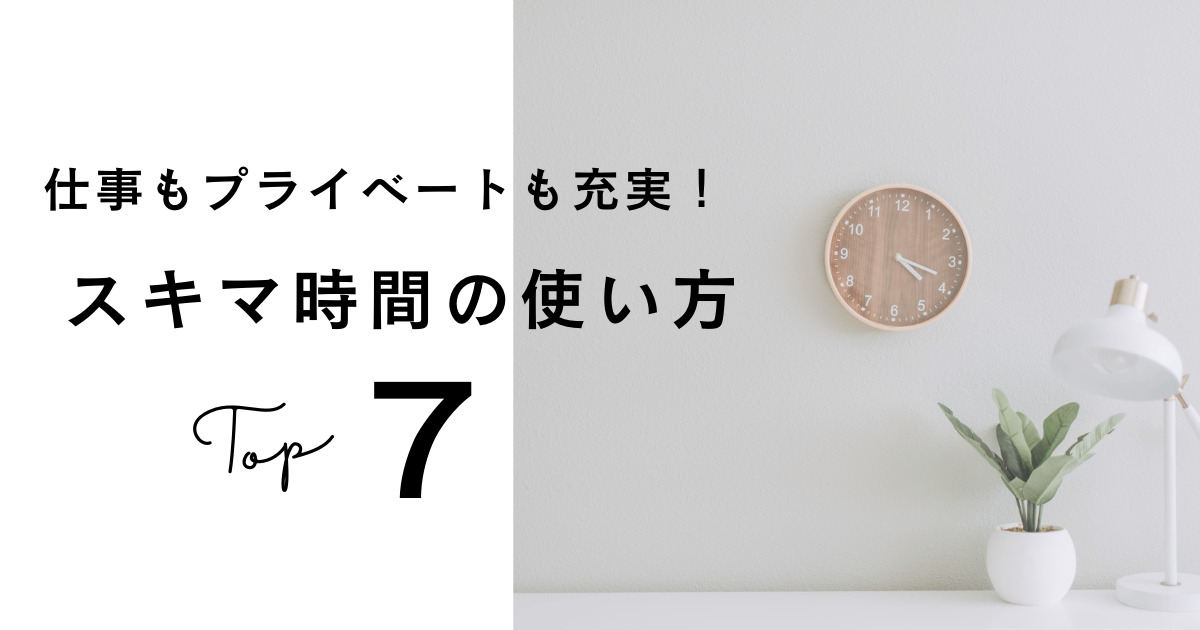
自分の考えを押し付ける
読書によって自己肯定感が高まると、誰かに読書で得た知識や考えを伝えたいという気持ちになることがあります。
「この方法をすれば絶対にポジティブになれるから、あなたもやってみて」
「なんで行動しないの?始めないかぎり人生は変わらないよ」
確かに、あなたの言っていることは正しいかもしれません。
しかし、相手との温度差を考えずに自分の考えを押し付けてしまうと、相手を不快にさ、人間関係が悪化してしまう可能性もあります。
読書でモチベーションが上がっているのは良いことですが、冷静さを忘れずに周囲と接するようにしましょう。
悪い姿勢と視力の低下


長時間読書をしていると、姿勢が悪くなったり、目が疲れてきたりします。
ひどい場合には、視力の低下や肩こり、頭痛などの原因にもなります。
そうならないためにも、適度な休憩を取り、ストレッチなどの軽い運動を取り入れるようにしましょう。
また、長時間座りっぱなしは健康に悪影響を与えるため、立ちながら読書するのもおすすめです。
インプットばかりになっている
読書は知識や学びを与えてくれますが、インプットばかりに注力していると、ただの物知りになってしまいます。
せっかく学んだことは、実際に行動に移して、自身のスキルアップや成長につなげることが大切です。
読書で得た知識をアウトプットすることによって、より理解が深まり、記憶にも残りやすくなります。
インプットとアウトプットのバランスを意識しながら読書に取り組みましょう。
おすすめはインプット3割、アウトプット7割です。
まとめ
以上、読書初心者が陥りがちな読書の罠について紹介してきました。
読書は人生を豊かにする力を持っています。
しかし、読書の罠に陥ってしまうと、せっかくの読書が台無しになってしまいます。
今回紹介したポイントを参考にして、読書を最大限に活かし、自分自身を成長させていきましょう。